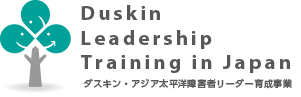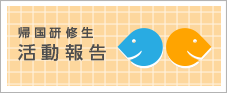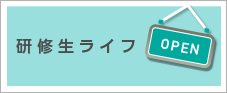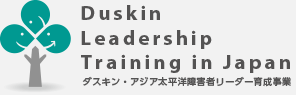- HOME
- 帰国研修生情報
- 23期生 リエカ・アプリリア・ヘルマンシャ
- ファイナルレポート
最終レポート
リエカ・アプリリア・ヘルマンシャのファイナルレポート
日本に到着して
日本に来るまえ、私はダスキンリーダーシップ研修プログラムについて何も知りませんでした。第二期ダスキン研修生であり、先輩でもあるガルー・スクマラさんに、2020年にダスキンのプログラムに応募してはどうかと勧められました。しかし、同年コロナ禍が世界を襲い、WHO(世界保健機関)が国際便の運航を禁止したため、研修生の選定に遅れが生じました。選定プロセスは2023年にようやく再開し、私は晴れて条件を満たし、選定試験も面接も合格することができました。そしてやっと、生まれて初めて外国に飛び立てることになりました。インドネシアのジョグジャカルタから、シンガポール経由で大阪に向かい、2023年10月23日、関西空港に降り立ちました。
日本では一日目にして、日本とインドネシアとの違いを多く目にしました。たとえば挨拶のやり方です。インドネシア人は両手を合わせるか、右手を左胸に置いて挨拶しますが、日本の人はお辞儀です。インドネシアの季節は乾季と雨季の二つですが、日本は春夏秋冬の四季です。それとともに驚いたのは、日本がどれほど清潔で、秩序だっていて、インクルーシブであるかでした。いろいろな障害がある人でも、一人であちこち移動していました。込んだ公共の場所でも、誰もがきちんと並んでいました。日本のトイレのきれいさは驚嘆に値します。素晴らしいです!さらに、いろいろな教育テーマのもとにいくつか観光地も訪れました。素晴らしかったです。私はインドネシア人ですが、他の研修生はスリランカとバングラデシュから来ていました。スリランカから参加の女性は視覚障害 (黄斑ジストロフィ)で、バングラデシュからの男性は肢体障害(シャルコー・マリー・トゥース病)でした。

日本語と日本手話
日本に来る前、私はひらがなとカタカナの練習、それに日本手話,を8回のZoomミーティングで習っていました。そのあとは、聴者の先生と、ろう者の先生から直接日本語と日本手話を三カ月学びました。レッスンではひらがな、カタカナ、漢字を書く練習が続きました。日本語の文法を覚えるのはかなり難しかったですが、ろう者の先生は次々に新しい手話を教えてくださり、より長い文章を読んだり書いたりする練習をするように、と励ましてくださいました。日本語と日本手話のレッスンのおかげで地元コミュニティの人たちとよりたやすく、迅速に意思疎通できるようになりました。日本手話のほうが日本語よりうまくなりましたが、これからも両方の勉強を続けるつもりでいます。
ホームステイ
佐賀県では、一週間ホームステイを経験しました。井上さんのお宅で、ゲストのひろしさん、みやびさんと共に新年をお祝いしました。とても楽しかったです。田舎は心も頭もすっきりして、自然の空気を吸うことができ、田舎の雰囲気が大好きになりました。井上さんのお宅では交換留学生の話をいろいろして、ホームステイが終わる頃には本当の家族のようになりました。井上さんは漁師の仕事をしていて、家に生の魚を持ち帰り、料理しています。滞在中は井上さんが獲ってきた鯨肉もご馳走になりました。鯨を食べたのは初めてでした。インドネシアにも鯨はいますが、保護種になっているので、獲ったり食べたりはできないのです。

私の経験したこと
1. ダスキンミュージアム
ダスキンミュージアムでは、ドーナツ作りの最初から終わりまで切って、型をとって、という過程を実際にトライしてみました。揚げるところも見学しました。ドーナツもチョコレートとバニラのトッピングが乗っていて好きにカスタマイズできるものなど、いろいろな形やフレーバーのものがありました。他の研修生やJSRPD(日本障害者リハビリテーション協会)のチームと研修を受け、非常に楽しくおもしろかったです!

2. スキー研修
新潟では生まれて初めて二日間スキーにトライしました。スキーの先生、同期の研修生、JSRPDのチームも一緒でした。とても楽しかったです!雪に触ったのも初めてで、かき氷のような手触りでした。
個別研修
個別研修では東京の日本ASL協会に行きました。最初から最後までプレゼンテーションのスキルを研修し、情報収集やプレゼンのときの立ち方、聴衆を前にし手話で行なうプレゼンテーションの方法などを学びました。聴者とは異なる、ろう者のプレゼンの見せ方を学ぶことができました。プレゼンテーション能力が向上しました。
デフNetworkかごしま
デフNetworkかごしまには、4つの事業がありました。一つ目は、デフキッズです。子どもたちは、ろう学校の授業が終わったら、デフキッズにやってきます。そして、宿題をしたり、みんなで遊んだり、おしゃべりをしたりします。スタッフは手話で子どもたちとコミュニケーションをとるので、子どもたちは、スタッフの説明を全部理解できます。二つ目は「ぶどうの木」です。高齢ろう者やろう重複の方が、手芸品を作っていました。ぶどうの木は、仕事をする場としてだけでなく、手話で楽しくお話ができる居場所としても機能していました。三つめは、薩摩わっふるです。ここでもろう者やろう重複の人たちが手話でコミュニケーションを取りながら働いていました。工賃を得て、きちんと生活できていると聞き、ろう者が安心して働ける場所の重要性を感じました。私も実際にワッフルを作ってみましたが、とてもおいしかったです。最後は、グループホームです。建物は男女で分かれていて、ろう重複の人たちが暮らしています。入居者は、自立に向けて、親元を離れ、少しずつステップを踏みながら、掃除や洗濯などできることを増やしていっていました。このように多岐にわたる事業を行っているデフネットかごしまですが、各事業のリーダーが、全員ろう者であることも大変印象的でした。

大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター
このセンターではろう者と聴者のリーダーが効果的に協力する仕組みができています。
こめっこ
こめっこは、楽しい活動を通して、聞こえない乳幼児が手話を身につけられる所です。ここでは、ろう児だけでなく、その親のサポートも行われている点が興味深かったです。例えば、親たちを対象とした手話教室が開かれているので、家庭でも親子が手話でコミュニケーションをとることができます。また、相談業務も行われているので、親たちは聞こえない子どもを育てる不安を解消することができます。
明晴学園(東京)
私は来日する前からバイリンガル教育を行っている明晴学園のことを知っていました。私は主に、幼稚部(4~5歳)で研修を行いましたが、子どもたちは手話が堪能で、いろいろな話題で話すことができるのを見て驚きました。明晴学園には幼稚部から中学部までの学生が在籍しており、年齢や学部を越えて学生同士が交流できるのも魅力的に感じました。

私の研修の目標は、日本におけるろう児の指導方法やろう児を持つ親について学ぶことでした。インドネシアと日本の相違点として気づいたことが2つありました。
1つ目は、手話で学べる環境の有無です。インドネシアにはろう児が手話で学べる学校がありません。日本では、ろうの先生が手話で学習内容を伝えます。子どもたちは先生の説明を見て、質問をしていました。このような対話を通した教育の利点は、子どもが理解しているか確認しながら授業を進められる点です。インドネシアでは、子どもたちがわからないことを教師がわからないまま、授業が進められています。
2つ目は、相談支援の有無です。日本には、聞こえない子どもが生まれたとき、その子をどうやって育てればいいのかを相談できる場所があります。相談を通じて、コミュニケろう児とのコミュニケーション方法として手話があることを知り、両親が手話を学べる場所も提供されます。インドネシアでは、相談支援が行われていません。家庭内でのコミュニケーションがうまくいかないことから、ろう児は一人で思い悩み、家に引きこもってしまうという事例がたくさんあります。

将来の計画
将来の計画は、ろう児とその親が相談できるプログラムを作ることです。また、ろう者の学習のための学校や学習センターを作りたいと思っています。この考えは、明晴学園でさまざまな年齢の子どもたちが、年上や同い年の他のろうの生徒と自由にコミュニケーションしているのを見たことが理由でした。インドネシア全土で手話を使ってろう児と対話することについての意識が向上することはとても重要だと思います。早期教育を左右するからです。とくにろうの子どもを持つ親は毎日子どもと対話するために手話を学ぶことが重要だと思います。 また、障害のある人たちが自分たちの問題を解決するのを力の限り手助けしたいと思います。Bismillah(ビスミラ:慈悲深く慈愛深い神の御名において。)
まとめ
ダスキンの研修のさまざまな活動を通じて、集団研修でも個別研修でも、気づきを得る瞬間が多くありました。日本では数多くの新しい経験をし、知識とアイディアを得ることができました。ここで学んだ知識から得ることは多く、力の限り良いリーダーとなって、この気づきを他の人たちと分かち合いたいと思います。多くの日本の皆さん、なかでもダスキンの皆さんからの前向きな動機付けと支援のおかげで熱意がいっそう強くなりました。
ダスキン愛の輪基金およびJSRPDの皆さんには、日本の研修の間このような貴重な機会を与えていただいたことに心から感謝を表明したいと思います。集団研修、個別研修の期間中に培われた友情と協力関係を今後も維持し、より強いものとしていきたいと願っています。