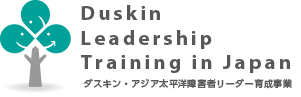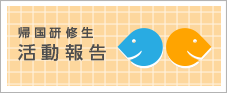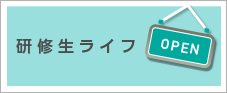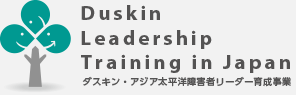- HOME
- 帰国研修生情報
- 23期生 ジョヒルル・イスラム
- ファイナルレポート
最終レポート
ジョヒルル・イスラムのファイナルレポート
バリアを破る:変化をもたらすリーダーシップへの道づくり
はじめに

私は初めてのダスキン研修プログラムのおかげで、さまざまな内容の研修セッションをどのように計画するのかを深く理解することができました。 リーダーシップについて理解したことは、リーダーシップとはいろいろな情報を得ながら継続的に伸ばしていくものだということです。本研修プログラムは様々な知識に溢れていました。私にとっては自分の視野を広げ、リーダーシップやインクルーシブ性についての自分の見方に多大な影響を与えるものでした。
また、一人で、車いすで外に出かけてみることで、バリアフリーの概念の大切さを痛感しました。理想の社会とは、すべての公共スペースがバリアフリーで、障害者をはじめ誰もが、問題なく外で食事を楽しんだり家族と有意義な時間を過ごしたりできる社会でしょう。このようなアクセシビリティとインクルーシブの視点があれば、誰もが社会的・文化的な活動に参加できるようになります。
私は世界に名だたる日本の丁寧なサービス(おもてなし)や他者への敬意、和を重んじる心、生活のあらゆる点をよくしようと努力することなどを見て日本が大好きになりました。
肢体障がい者として、私はよく移動の手段や道路、そしてとくにアクセシブルなトイレのことを考えなければなりません。バリアフリー展では、ベッドやトイレ、浴室、それから移動の手段に至るまで日本の素晴らしい技術革新を目の当たりにしました。障害のある人たちの生活をよくするにはどれだけアクセシブルなデザインが重要かが、これらのイノベーションを見てよくわかり、私自身もインクルーシブ性を促進するのに尽力したいという気持ちがより強くなりました。
日本語研修:成長の旅路
東京の戸山サンライズでは三カ月、集中的に日本語研修を受けました。日本語を身につけるため勉強に没頭しましたが、わかったのはこの勉強がただ言語スキルを身につけるだけのものではなくて、日本の他者への敬意や和を重んじる心、細部まで緻密に物事をやることなどの日本文化を理解するためのステップでもあったということです。先生方は素晴らしかったです。忍耐強く教えてくださり、日本文化についての説明もしてくださったため、学びがいっそう豊かなものとなりました。日本語を理解して話せるようになったので、より流暢に日本語を使えるようになりたいと思うようになりました。
ホームステイの思い出
日本の南部、九州にある宮崎県では、宮崎の有名な美しい自然を体験しました。文化を吸収できる拠点、自立応援センターYah!Doの山之内さんが温かく迎えてくださり、宮崎の素晴らしい砂浜や、海沿いの景色のよいところへドライブに連れていっていただき、宮崎にすっかり魅了されました。山之内さんの温かさ、おもてなしのおかげで、ここが平和な自分の居場所であると思える忘れられない思い出となりました。あまりに素晴らしかったため、宮崎のエッセンスをまとめた動画「Amazing Miyazaki」を作るに至りました。
障害者自立応援センターYah!doの建物は伝統的な和の美しさと、現代の機能性を兼ね備えたもので、静かな山の景色の中で過ごした体験は忘れられません。また静かな浜辺と荘厳な山々に囲まれて新年を迎えることができたのは、とても贅沢なことでした。比類のない宮崎の静けさと自然の素晴らしさに大変胸を打たれ、またこの地をいつか訪れたいと強く願っています。
日本の食べ物:文化と日本の物の見方について
日本では、ハラールのラーメン、焼肉、そば、うどん、寿司、刺身、タコ、野菜、魚の天ぷらなど有名な日本食を味わいましたが、国に帰ってまた食べたいと思うのは、ツナとマヨネーズのおにぎりです。
初めてのスキー体験
初めての新潟でのスキー体験に私は期待と興奮の入り混じった気持ちで臨みました。とても寒く身体的にも大変でしたが、スキーの方法を習って障害者のためのバイスキーを使ったことは、頑張ることと決意について学ぶかけがえのない経験でした。メディアにも取り上げられ、ひるむことなく信念をもって問題を克服し、自分のゴールを目指すことの大切さを学びました。
集団研修
集団研修では福祉サービス、障害者運動の歴史、ユニバーサルデザインの趣旨、日本のさまざまな障害者支援システムについて学びました。障害者を支援する体系的な活動を包括的に説明するセッションで、インクルーシブな政策や活動の重要性が分かりました。また、ピアサポート、内省、人生曲線なども学び、障害者の経験する課題や克服についての貴重な視点を学びました。
研修では、障害者の支援において、社会的、経済的、心理的な側面を統合した全体的なアプローチが大切であることが強調されていました。こうした多面的な視野があることを知り、障害者の心身の健康やエンパワメントにさまざまな要因がどうかかわっているのかより深く理解できるようになりました。
個別研修
DAISY(アクセシブルな情報システム)技術について学んだことは目から鱗の経験でした。DAISYは、視覚障害者が情報にアクセスできるように考え出された技術です。介助技術がどのような可能性を開くのか、垣間見た気持ちでした。障害者向けに設計された、テキストをオーディオに変換する技術や画像を説明する技術などを理解したいと思いました。しかし、DAISYのようなかけがえのないソリューションが存在するにもかかわらず、今のところそれによって助かるはずの人たちすべてに行き届いていないことも現実です。今後もDAISYについては勉強を続け、DAISYの効果や、改善の余地があるとすればどこなのかなどについて理解を深めていきたいと思っています。

個別研修ではハンズオン東京も訪れ、革新的なフードトラックの概念を教えていただきました。食べ物の届かない場所に食べ物を届けるフードサービスを見学して、社会的なニーズにどう対応するか考えるうえで独創的なアイディアがどれほど力を持つかがよくわかりました。ハンズオン東京の独創的なアプローチに感銘を受けましたので、バングラデシュの実情に合わせたフードトラック事業をバングラデシュでも作っていきたいと強く思っています。現地固有の課題や可能性を分析して、現地のニーズや嗜好に合った独創的なソリューションを提供していきたいと思います。
研究室での機械学習体験

神奈川工科大学の情報システム学科三枝研究室では高度介助技術について学び、障害者支援を劇的に変える最先端技術を目の当たりにしました。私もAIとロボット工学に関与して、効果的で意味のある解決策ができるよう技術革新とユーザーのニーズの間のギャップを埋めていきたいと思います。バングラデシュでは技術セクターが急速に成長していますが、AIに関して私は非常に前向きですので、今回の経験を活かしてこの分野にインパクトある形で変化をもたらしていきたいと思っています。
変化に向けたビジョン

私のビジョンは、バングラデシュで自立生活センター(CIL)を立ち上げて、社会的な保護のシステムを変え、障害者をエンパワーし、障害者が完全に社会に溶け込めるようにすることです。メインストリーム協会、夢宙センターなどの皆さんと協力して、永続的な変化をもたらしたいと強く思っています。すべての人のためのバリアフリー社会の大切さを認識したので、こうした目的に向かって歩みを進めるべく、インクルーシブな研修セッションと戦略会議を立ち上げました。
学んだこと、そして将来行いたい取り組み
メインストリーム協会、自立支援センターぱあとなぁ、自立生活夢宙センターの存在は、困難に見舞われながらもどれだけ大変な努力をもって設立され、障害者の権利運動がいかに熱意を持って行われたかを如実に示しています。アクセシビリティの問題や、社会の態度といったさまざまなハードルを克服するためには弛みない、揺るぎない努力が必要でしたが、日本のリーダーの皆さんの揺るぎない献身によって、バリアフリーのアクセスに象徴される、よりインクルーシブな環境が造られたのです。
また、日本のお宅にお邪魔したことで、日本の障害者の人たちが家庭でどのように過ごしているかを実体験することができました。家庭の中でいろいろな創意工夫がなされているのを見て、障害者のコミュニティが直面する現実的な問題もより深く理解できました。日本の家庭でもアクセシビリティはこれまでずっと課題であり続けているものの、自立生活センターの活動が、政府の社会福祉活動の後押しをしてきました。これらの体験から、バングラデシュでも同じような運動の波が起こせる可能性を感じます。
バングラデシュでは、現地の実情に合わせた自立生活センターの設立が喫緊の課題です。ワークショップを開催したり調査をしたりして、広く障害者のコミュニティが必要としていることや希望していることを探る必要があります。そしてそうした取り組みには、国のリーダーや草の根のネットワーク、都市部や地方のコミュニティ、教育機関などを巻き込んで、インクルーシブ性が担保できるよう注意を払わねばなりません。多様な視点を得て、広く理解を深めるには、政府担当者や団体代表とウェビナーや相談を重ねていくことが肝要です。
また、自立生活センターを長期にわたって存続させていくには、持続可能な資金の獲得も重要です。センターを設立し、その後の活動も続けていくには、政府の助成金から私的な寄付金にわたるまでさまざまな資金源を模索する必要があります。私の日本での研修は、日本の団体と貴重な協力関係を作るきっかけとなりました。協力して活動したり意見を交換したりすることで、バングラデシュの自立生活センターの発展につなげていけると考えています。
集団研修を終えたあとは、プロポーザルや行動計画を作成したり、日本財団やJICAといった機関との関係を築いたりしました。これらの活動をまとめたのが最終報告です。報告書では、バングラデシュに戻ってから障害者の権利擁護活動を進めていくうえでの私たちの共通のゴールや願いをまとめました。「難民を助ける会」や「シャプラニール=市民による海外協力の会」とも協力関係ができたことで、現存する人道的な支援構造への足並みが揃い、バングラデシュの障害者権利運動が実質的な成果を上げられるよう、私たちの活動を強化してくれるものと思っています。

まとめ
2024年7月13日、私たち研修生は、忘れ得ない経験の数々と、ダスキン愛の輪財団の確固とした支援への限りない感謝の気持ちを胸に、日本を後にしました。探求と協力がもたらす変化がどれだけ大きいかを露わにしてくれた旅でした。
戸山サンライズは単なる研修センターではなく、人との深い結びつきと理解の生まれた場所でした。私たち研修生を実質的なリーダーへと育ててくださったJSRPDに感謝します。
この経験を胸に、ここで誓いを新たにしたいと思います。「私ができなければ、誰もできない」この信念を思い起こし、どんな困難にも負けずに立ち向かい、決意をもって壁を取り払っていく覚悟です。
ダスキンの皆さん、胸躍るお知らせや活動の成果をお話できるように、皆さんとの再会を楽しみにしています。それまでどうぞお元気で、これからを楽しみにしていてください!